9歳という年齢は、思考力・感情・対人関係のすべてが大きく成長する大切な時期です。その発達を楽しく支える手段として注目されているのが、ボードゲームです。特に「ボードゲーム 発達支援 9歳」と検索している方の多くは、お子さんの社会性や考える力、対話力といった力を遊びの中で育てたいと考えているのではないでしょうか。
この記事では、社会性を育てる協力型ボードゲームや、柔軟な発想を伸ばす知育ゲームの魅力に加え、状況把握を学べる推理系ボードゲームなど、具体的なジャンルごとの効果を紹介します。また、感情理解ゲームで思いやりを育てたり、論理思考ゲームで考える力を伸ばしたりといった、9歳児の発達段階に合わせたゲーム選びのヒントも網羅しました。
さらに、小学生におすすめの集中力ゲームや、コミュニケーションゲームで対話力を強化する方法、発達支援に活かせる多人数ゲーム活用法など、家庭でも実践しやすい活用例も取り上げています。ルールの理解が育つ知育ゲームの工夫や、社会性と反論受容を学ぶプレイ設計、プレイヤーの工夫で広がる学びの効果など、実践的な視点も交えながら、日常生活に活かせる発達支援の視点まで丁寧に解説していきます。
遊びながら力を育てる。そんなボードゲームの可能性を、ぜひ一緒に探っていきましょう。
- 9歳児の発達支援に効果的なボードゲームの種類
- 協調性や対話力など社会性を育むゲームの特徴
- 思考力や集中力を高める知育ゲームの選び方
- 日常生活に応用できる遊び方と親の関わり方
ボードゲームの発達支援で9歳に効果的な遊び方


- 社会性を育てる協力型ボードゲーム
- 柔軟な発想を伸ばす知育ゲームの魅力
- 状況把握を学べる推理系ボードゲーム
- 感情理解ゲームで思いやりを育てる
- 論理思考ゲームで考える力を育む
社会性を育てる協力型ボードゲーム

協力型ボードゲームは、9歳児の社会性を自然に育むための有効な手段です。勝敗を競うのではなく、チームで目標達成を目指すスタイルが特徴で、仲間との意思疎通や思いやりの大切さを実感しやすくなります。
たとえば「おばけキャッチ」や「パンデミック(子ども向けアレンジ)」などのゲームでは、それぞれのプレイヤーが役割を担い、全体の戦略を練りながら行動することが求められます。このような場面では、発言のタイミングや仲間の意見をどう受け止めるかが重要になり、自然とコミュニケーション力や共感力が磨かれていきます。
ただし、協力型とはいえ全員が勝敗に責任を持つ構造なので、勝てなかったときに誰かを責めるといったネガティブな空気が生まれやすい面もあります。そのため、遊ぶ前に「みんなで挑戦するゲーム」であることをしっかり伝えるなど、大人のサポートも大切です。
協力型ボードゲームは勝ち負けを超えた関わり合いの中で、子どもたちに社会性を体感させてくれる貴重なツールといえるでしょう。
おばけキャッチ

『おばけキャッチ』は、瞬発力と判断力を試される早取り型のカードゲームです。プレイヤーは、場に並べられた5種類の木製コマ(おばけ、椅子、本、ビン、ネズミ)の中から、カードに描かれたイラストの情報を瞬時に読み取り、正しいコマを素早く掴み取ることを目指します。
カードには2つのイラストが描かれており、状況に応じて「正解のコマ」を導き出す必要があります。イラストに描かれているコマが、正しい色と形であればそれが正解ですが、色も形も一致しない場合には、カードに描かれていない色・形のコマを選ぶ必要があります。この「消去による推論」がゲームの独自性を生んでおり、直感だけでは勝てない頭脳戦としても楽しめます。
出典:Youtube ボードゲームルール超簡単説明より
| ジャンル | スピード系 × アクション系 × 瞬発力勝負 |
| 効果 | 集中力と反応速度が鍛えられます |
| 人数 | 2〜8人 |
| 時間 | 約20〜30分 |
| 特徴 | シンプルなルールながら、奥深い心理戦と瞬発力勝負が展開 |
パンデミック

『パンデミック』は、世界中に蔓延する4種類の感染症に立ち向かう、協力型の戦略ボードゲームです。プレイヤーはそれぞれ異なる専門職(科学者、衛生兵、通信司令員など)を担当し、世界各地を移動しながら感染の拡大を防ぎ、治療薬の開発を目指します。
毎ターン、感染はランダムに広がり、時には「エピデミック」によって急激な拡大が起こることも。プレイヤー同士の連携と役割の活用が勝敗を左右し、全員で勝つか、全員で負けるかという緊張感が魅力です。限られた時間とリソースの中で、世界を救えるかどうかはあなたたちの判断と協力次第!
出典:Youtube プロボドより
| ジャンル | 協力型戦略ボードゲーム(カードピック、エリア移動、役割分担) |
| 効果 | チームビルディング、戦略思考、役割理解、コミュニケーション力の向上 |
| 人数 | 通常版:2〜4人(拡張で最大6人まで対応) |
| 時間 | 約45分 |
| 特徴 | プレイヤー全員が同じ目的で協力する |
柔軟な発想を伸ばす知育ゲームの魅力

知育ゲームは、9歳の子どもにとって柔軟な発想力を刺激する絶好のツールです。あらかじめ決まった解答だけを導き出すのではなく、複数の考え方や解決手段を許容するゲームは、子どもの創造性や独自の視点を引き出してくれます。
たとえば「ナンジャモンジャ」や「ウミガメの島」のようなゲームでは、独自の名前付けや論理展開を考えることが求められます。そのたびに子どもは自分なりのアイデアを発信し、周囲の反応を受けながら発想を柔軟に調整していく体験ができます。
このような遊びの中では、正解が1つではないため「間違えたらどうしよう」という不安を感じにくく、安心して自由に考える力を発揮できます。さらに、他の人のアイデアに触れることで、自分の視野も広がりやすくなります。
ただし、子どもによっては自由度が高いルールに戸惑うこともあります。そのような場合は、大人が簡単な例を示したり、「自由に考えていいよ」と声をかけることで安心感を与えることができます。
知育ゲームはルールの中に創造的な余白があり、9歳児の柔軟な思考を自然に伸ばしてくれる点が魅力です。
ナンジャモンジャ・シリーズ(ナンジャモンジャ・シロ / ミドリ)
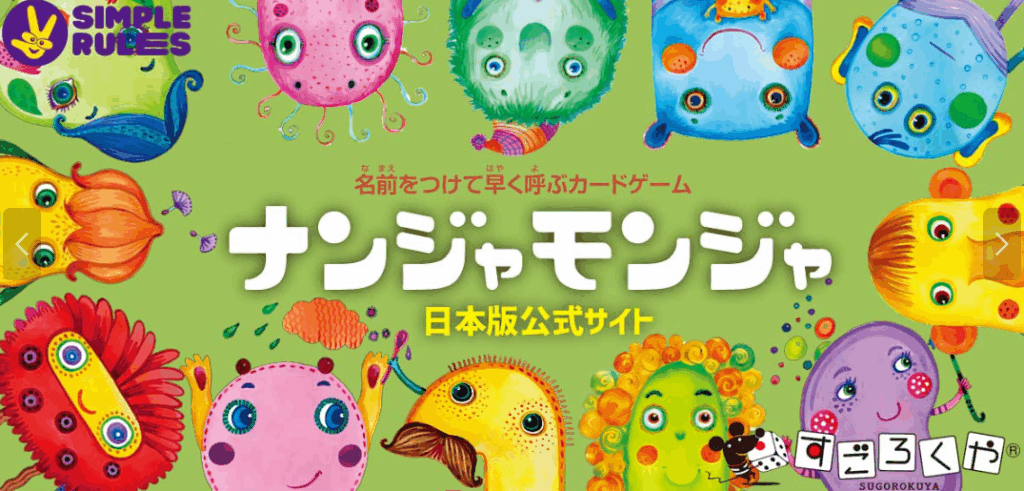
『ナンジャモンジャ』シリーズは、ロシア生まれの爆笑記憶系カードゲーム。プレイヤーは順番にカードをめくり、描かれた謎の生物「ナンジャモンジャ族」に自由な名前をつけていきます。
同じキャラが再登場したら、誰よりも早くその名前を叫んだ人がカードを獲得。記憶力・瞬発力・ネーミングセンスが試される、子どもから大人まで盛り上がれる傑作です。
出典:Youtube QuizKnockより
| ジャンル | パズル/スピード系 |
| 効果 | 記憶力・注意力・瞬発力の向上 |
| 人数 | 2〜6人 |
| 時間 | 約15分 |
| 特徴 | 子どもが大人に勝てることも多く、世代を超えて盛り上がる |
ウミガメの島
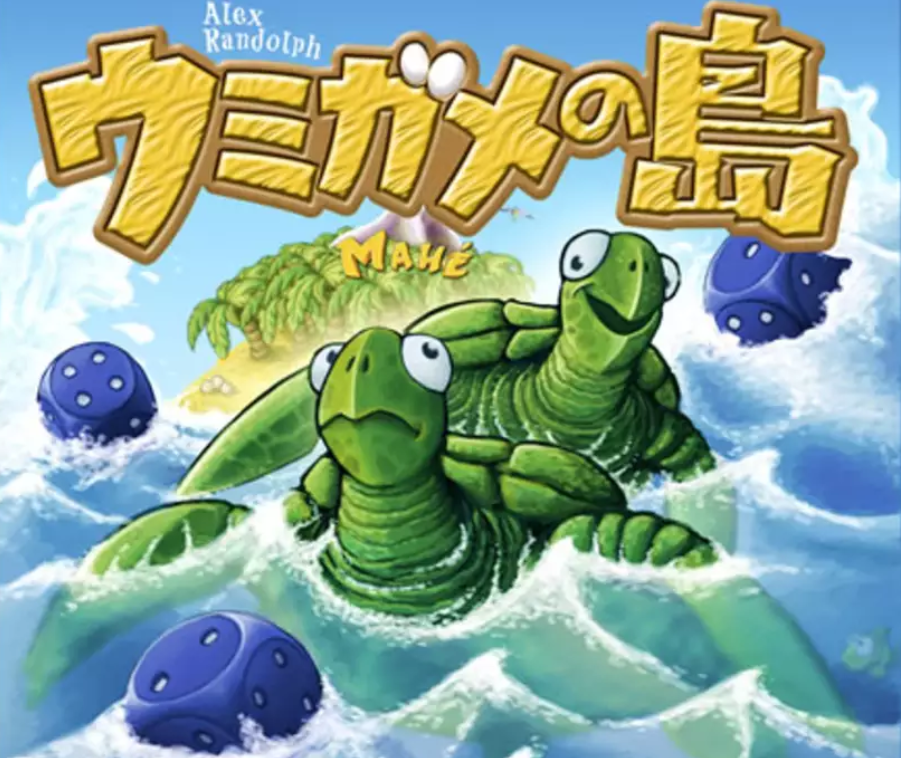
『ウミガメの島』は、サイコロを振って自分のカメを進め、島を一周することで卵カード(得点)を獲得していくレース型すごろくゲームです。サイコロを最大3個まで振ることができ、振った数に応じて進む距離が変わりますが、合計が8以上になるとスタート地点に戻されるという“チキンレース”要素が盛り込まれています。他のカメの上に乗ることで一緒に移動できる「おんぶ」ルールもあり、戦略と運が絶妙に絡み合う展開が魅力です。
出典:Youtube アナログゲームアドバイザー 大ちゃんより
| ジャンル | ダイスロール/スピード系 |
| 効果 | 算数的思考力の育成・注意力・協調プレイの体験 |
| 人数 | 2〜7人 |
| 時間 | 約20〜30分 |
| 特徴 | サイコロの個数 × 合計値で進む距離が決まるため、掛け算の感覚が自然に身につく |
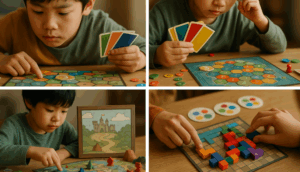
状況把握を学べる推理系ボードゲーム

推理系ボードゲームは、9歳の子どもが複雑な状況を整理し、自分なりに論理的な仮説を立てる力を育むのに適しています。ルールの理解だけでなく、相手の行動や情報の変化に目を配る必要があるため、自然と状況把握力が養われます。
代表的なゲームとしては「犯人は踊る」や「ラブレター」などがあり、どちらも限られた情報の中から相手の意図を読み取り、最適なタイミングで行動することが求められます。このような体験を通して、子どもは「今、何が起きていて、自分はどう動くべきか」を考える力を高めることができます。
一方で、情報量が多すぎると混乱してしまうこともあるため、最初はプレイ人数を制限したり、ルールを簡略化して始めるとスムーズです。また、推理が当たらなかった場合でも「そこまで考えていたんだね」と結果ではなく過程を認める声かけが大切です。
推理系ボードゲームは、状況の流れを読む力と先を見通す視点を同時に鍛える貴重な教材として、9歳児の成長に役立ちます。
犯人は踊る

『犯人は踊る』は、たった1枚の「犯人カード」をめぐってプレイヤー同士が駆け引きを繰り広げる心理戦型カードゲームです。プレイヤーは手札からカードを1枚ずつ出しながら、犯人カードの所在を推理し、探偵カードやいぬカードで犯人を当てることを目指します。
一方、犯人カードを持っているプレイヤーは、アリバイカードで身を守ったり、カード交換で所在をぼかしたりしながら、最後の1枚として犯人カードを出せれば勝利。「犯人は誰だ?」という緊張感と、カードが移動することで生まれるドラマが魅力の、短時間で盛り上がるパーティーゲームです。
出典:Youtube TRAMPLE GAMESより
| ジャンル | 推理ゲーム・心理戦・正体隠匿系カードゲーム |
| 効果 | 推理力・観察力・駆け引き・ブラフ・演技力の向上 |
| 人数 | 3〜8人(5人以上が特に盛り上がる) |
| 時間 | 約10〜20分 |
| 特徴 | カード交換や効果によって、犯人役が次々と変わるスリリングな展開 |
ラブレター
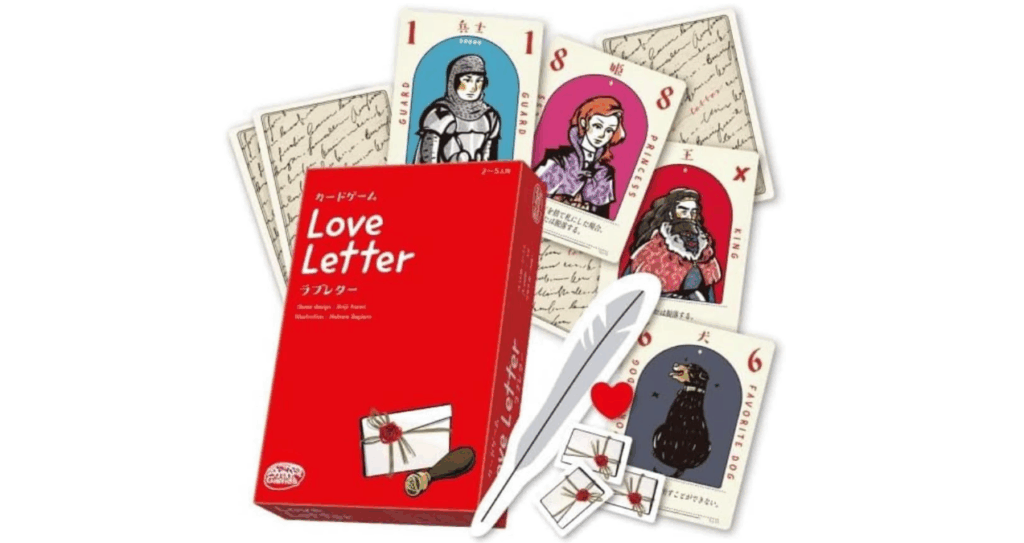
『ラブレター』は、たった1枚の手札で繰り広げる心理戦カードゲームです。プレイヤーは姫に恋する若者となり、城の人物(カード)の力を借りてラブレターを届けることを目指します。毎ターンカードを1枚引き、2枚のうち1枚を使って効果を発動。相手の手札を推理して脱落させたり、自分の身を守ったりしながら、最後まで生き残るか、最も高い位の人物にラブレターを託した者が勝者となります。
シンプルなルールながら、記憶力・推理力・駆け引きが試される奥深いゲームで、初心者から上級者まで幅広く楽しめます。短時間でプレイできるため、何度も繰り返し遊べるのも魅力です。
出典:Youtube ボドゲマンの愛と笑いのボードゲームレシピより
| ジャンル | 心理戦・読み合い・正体隠匿系カードゲーム |
| 効果 | 推理力・記憶力・観察力・駆け引き・戦略思考の向上 |
| 人数 | 2〜4人 |
| 時間 | 約5〜10分 |
| 特徴 | 相手の行動や捨て札から手札を推理する心理戦が展開 |
感情理解ゲームで思いやりを育てる

9歳は、自分の気持ちだけでなく相手の感情にも目を向けはじめる年齢です。この時期に感情理解を促すアプローチとして、遊びの中で気持ちを考える体験が効果的です。ゲーム形式であれば、子どもも自然に関心を持ちやすく、感情表現や共感力を楽しく育むことができます。
例えば、イラストカードやストーリーカードを使って、「この子はどう思っているかな?」と考えるような活動では、正解を求めるのではなく「気づく力」を引き出すことができます。「悲しそうに見える?」「驚いているかも」といった子どもなりの発言を受け止めることで、他者の視点に立つきっかけが生まれます。
こうしたやり取りは、友達との関係や家族との日常会話にも良い影響をもたらします。相手の立場を想像して行動する姿勢が、無理なく育っていくのです。ただし、感情に向き合うことに戸惑いを感じる子もいます。その場合は、「自分の感じ方も相手の感じ方も、どちらも大切だよ」と伝えてあげることで、安心して話せる環境が整います。
感情理解をテーマにしたゲームは、単なる遊び以上の意味を持ちます。9歳という感受性が豊かになる時期に、思いやりの土台をつくる体験として、家庭や教育現場で取り入れてみる価値があります。
感情理解ゲームは9歳という思考と感情が伸びてくる時期に、他者視点を養う貴重なサポートになります。ゲームを通して思いやりの土台を築くことができるでしょう。
論理思考ゲームで考える力を育む

論理思考ゲームは、物事を順序立てて考える力を伸ばすのに適しており、9歳児の知的発達をサポートする重要な要素です。「なぜそうなるのか」「どうすれば効率よく進められるか」といった過程を楽しみながら学べるのが大きな特徴です。
例えば「ウボンゴ」や「コードマスター」などのゲームでは、限られた条件の中で最適な手順を考える必要があります。間違えた場合も「次はこうやってみよう」と試行錯誤を重ねる中で、子ども自身が自分の考えを組み立て直す力を身につけていきます。
このような繰り返しの中で、「考え抜く楽しさ」や「試すことで理解が深まる」という感覚が芽生え、自然と思考に対する自信も育まれていきます。ただし、論理の流れが複雑すぎるゲームを選んでしまうと、かえって混乱を招いてしまう可能性もあるため、年齢に合ったレベルのものから始めるのがおすすめです。
論理思考ゲームは、正解に至るプロセスを意識する習慣づけになり、学習や生活全般に活かせる「考える力」を自然に育てることができます。
ウボンゴ
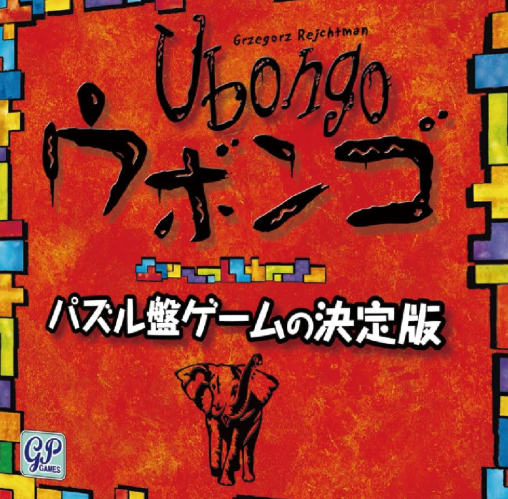
『ウボンゴ』は、制限時間内にパズルを完成させるスピード系ボードゲームです。プレイヤーは毎ラウンド、指定された形のピースを使って、自分のボード上の白い枠をぴったり埋めることを目指します。完成したら「ウボンゴ!」と叫び、順位に応じて宝石を獲得。9ラウンドの合計得点で勝者が決まります。
シンプルなルールながら、瞬発力・空間認識・集中力が試されるゲームで、子どもから大人まで幅広く楽しめます。ピースの裏返しや回転を駆使して解くパズルは、脳トレ感覚で何度でも挑戦したくなる魅力があります。
さらに、難易度の異なる面やシリーズ展開(3D版・ミニ版・エクストリームなど)も豊富で、プレイヤーのレベルに応じた遊び方が可能です。
出典:Youtube マーマン Asobi チャンネルより
| ジャンル | パズル系・スピード系・アクション系ボードゲーム |
| 効果 | 柔軟な思考力・空間把握能力・集中力と判断力・試行錯誤による問題解決力 |
| 人数 | 1〜4人 |
| 時間 | 約25〜30分(1ラウンドは約3分) |
| 特徴 | 制限時間内にパズルを完成させる・瞬発力と空間認識力が試される |
コードマスター

『コードマスター』は、プログラミング的思考を育てる1人用パズルボードゲームです。プレイヤーはアバター(自分の分身)を操作し、クリスタルを集めながらポータル(ゴール)へ導くための「プログラム」を構築します。使えるトークン(命令)は限られており、条件を満たす最適な手順を論理的に導き出すことが求められます。
このゲームは、NASAのプログラマーが考案した本格派。60問のステージは徐々に難易度が上がり、条件分岐やループ処理の概念も登場。まるでRPGのような世界観の中で、プログラミングの基礎を自然に体得できます
出典:Youtube ファブキューブ STEM チャンネルより
| ジャンル | プログラミング思考・論理パズル・知育ゲーム |
| 効果 | ・論理的思考力 ・問題解決力 ・順序立てて考える力 ・プログラミング的思考 |
| 人数 | 1人専用 |
| 時間 | 約10〜20分(問題の難易度による) |
| 特徴 | ・命令トークンを使ってアバターを動かす ・条件分岐やループ処理あり ・クリスタルを集めてゴールへ導く |
ボードゲームの発達支援で9歳に役立つゲーム選び

- 小学生におすすめの集中力ゲーム
- コミュニケーションゲームで対話力を強化
- 発達支援に活かせる多人数ゲーム活用法
- ルールの理解が育つ知育ゲームの工夫
- 社会性と反論受容を学ぶプレイ設計
- プレイヤーの工夫で広がる学びの効果
- 日常生活に活かせる発達支援の視点
小学生におすすめの集中力ゲーム

集中力を鍛えるには、短時間でも一つのことに意識を向け続ける体験が欠かせません。その点で、小学生向けの集中力ゲームは、遊びの中で「今ここに集中する」姿勢を育むのに非常に適しています。
例えば「スピードカップス」や「スティッキー」などのゲームは、手元の動きと視覚判断が連動しており、瞬間的な集中力が求められます。こうしたゲームでは、子どもがルールに沿って動きを止めたり、順番を正しく守ったりすることで、自然と集中を保つ練習になります。
また、勝敗があることで適度な緊張感が生まれ、遊びながら集中することの意味や達成感を体験できます。とはいえ、ゲームが速すぎたりプレッシャーが強すぎると、逆にミスが増えてモチベーションが下がることもあるため、子どもの性格に合わせた選び方が重要です。
集中力ゲームは楽しく遊びながら「一つのことに注意を向ける」練習ができ、学習や日常生活にも活かせる力を育てるうえで非常に効果的です。
スピードカップス
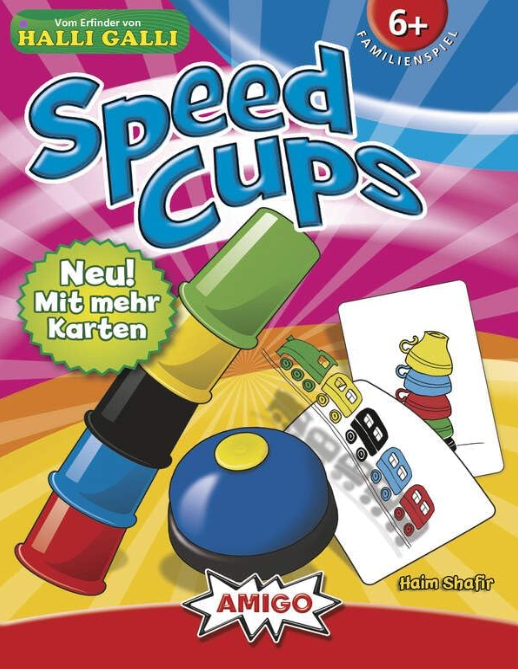
『スピードカップス』は、瞬発力と色認識力を競うリアルタイム・アクション系ボードゲームです。プレイヤーは5色のカップを使い、課題カードに描かれた色の順番通りにカップを「並べる」または「積む」ことで、いち早く正解を再現します。完成したらベルを鳴らし、正しく並べられていればカードを獲得。最終的にカードを最も多く集めた人が勝者となります。
出典:Youtube アジトベル 恵比寿のボードゲームカフェより
| ジャンル | スピード系・アクション系・知育ゲーム |
| 効果 | ・色認識力 ・反射神経 ・空間把握力 ・手先の器用さ ・判断力と集中力 |
| 人数 | 2〜4人 |
| 時間 | 約10〜15分 |
| 特徴 | 課題カードの色順にカップを並べる・縦か横か瞬時に判断・ベルを鳴らして勝負! |
スティッキー(HABA)

カラフルな棒をサイコロの色に合わせてそっと抜き取る、シンプルなのにドキドキが止まらないバランスゲーム。公式の対象年齢は6歳以上ですが、点数計算や戦略ルールを省略することで、3歳前後のお子さまでも十分に楽しめます。
棒を抜くだけなのに、大人もつい本気に….。集中力・手先の器用さ・順番を待つ力など、遊びながら育まれる知育要素がぎゅっと詰まっています。木製ならではの手触りと、カラフルなデザインも魅力。
親子でも、お友達同士でも、ルールを調整すれば幅広い年齢で盛り上がれる一品です。
出典:Youtube HAIR EY遊べる美容室より
| ジャンル | バランス系/引き抜き系 |
| 効果 | 指先の操作・慎重さ |
| 人数 | 2〜4人 |
| 時間 | 10〜15分 |
| 特徴 | 棒を崩さず引き抜こう!色を選んで指令通り、緊張感もあって楽しい。 |
コミュニケーションゲームで対話力を強化

コミュニケーションゲームは、9歳の子どもが「自分の意見を伝える力」と「相手の話を聞く力」を遊びながら身につけられる効果的な方法です。日常生活ではなかなか意識しづらいこのスキルも、ゲームというルールのある環境下では自然と練習できるのが特徴です。
例えば「ワードウルフ」や「ディクシット」のようなゲームでは、言葉を使って自分の考えや印象を相手に伝えたり、逆に相手の言葉から意図を読み取ったりする場面が頻繁にあります。特にディクシットでは、イラストに込めた想像を説明する必要があるため、自分の表現力と相手への伝え方を工夫する力が養われます。
このような経験を通じて、子どもたちは「話せばわかってもらえる」「相手にも伝えるタイミングがある」といった、対話の基本姿勢を学ぶことができます。ただし、勝ち負けにこだわりすぎると、言葉が荒くなったり、他人の発言を遮ってしまうこともあるため、大人が適宜フォローしてあげることも大切です。
このように、コミュニケーションゲームは、楽しみながらも実生活に活きる対話力の土台づくりをサポートしてくれます。相手とのやりとりをポジティブに捉える力が、将来的な人間関係にも良い影響を与えるでしょう。
ワードウルフ

『ワードウルフ』は、会話を通じて“仲間外れ”を見つけ出す正体隠匿系パーティーゲームです。プレイヤーにはそれぞれ似ているけれど微妙に異なる「お題」が配られ、少数派(ワードウルフ)は周囲と違うお題を持っています。自分が多数派か少数派かは分からないまま、自由なトークを通じて推理を進めていきます。
ゲームの目的は、多数派が少数派を見抜くこと、そして少数派が自分の正体を隠し通すこと。話題のズレや言葉の選び方から違和感を察知し、誰が“違う話をしているか”を見極める心理戦が展開されます。短時間で盛り上がり、初対面でも会話が弾むアイスブレイクとしても人気です。
出典:Youtube さまぁ〜ずチャンネルより
| ジャンル | 正体隠匿系パーティーゲーム |
| 効果 | ・コミュニケーション力の向上 ・観察力・分析力の強化 ・論理的思考・推理力の育成 |
| 人数 | 3〜6人 |
| 時間 | 約5〜10分 |
| 特徴 | ・お題の違いによる“違和感”を探る心理戦 ・自分が多数派か少数派か分からないスリル |
ディクシット

「抽象的なイラストを“言葉”で表現し、想像力でつながる心理・表現系ボードゲーム」
幻想的な絵柄のカードを使い、プレイヤーが順番に“語り部”となってヒントを出し、他のプレイヤーがそのカードを当てることを目指します。ただし、全員に当てられても、誰にも当てられなくても失点になるため、“ちょうどいい曖昧さ”が勝敗を分けるポイント。
出典:Youtube ボードゲームルール超簡単説明より
| ジャンル | ・表現・コミュニケーション系ボードゲーム ・心理戦・推理系ゲーム ・想像力・感性を活かすパーティーゲーム |
| 効果 | ・想像力・表現力のトレーニング ・コミュニケーションの活性化 |
| 人数 | 3〜6人 |
| 時間 | 約30分 |
| 特徴 | ・抽象的なイラストを“言葉・歌・ジェスチャー”で表現 ・“伝わりすぎず、伝わらなさすぎない”ヒントが鍵 ・語り部と回答者の心理戦が展開される ・毎回違う物語が生まれる、感性の違いが面白い ・拡張セットが豊富で、何度でも遊べる |
発達支援に活かせる多人数ゲーム活用法

多人数で行うボードゲームは、発達支援において社会性や協調性を育てる貴重な手段になります。1対1の対戦型とは異なり、複数の子どもが関わる場では、場の空気を読む力や順番を待つ忍耐力など、集団行動に必要なスキルが求められるからです。
例えば「キャプテン・リノ」や「犯人は踊る」などのゲームは、人数が多くなるほど盛り上がりやすく、自然と全員が場に参加できる仕組みになっています。順番通りに動く、仲間の意見に耳を傾ける、自分の出番を意識するなど、すべてが発達支援に直結します。
このとき特に重要なのは、ゲーム中に発生するトラブルや感情の起伏をどのように受け止めるかという点です。負けたときに悔しさを言葉にできなかったり、意見がぶつかったときに感情的になってしまうこともあるでしょう。そのような場面では、大人が「今どう思った?」「次はどうすればうまくできるかな?」と寄り添って声をかけることで、子ども自身が状況を整理する練習になります。
多人数ゲームを活用することで、単なる遊び以上の学びを得ることができ、子どもの社会的な成熟にもつながっていきます。
キャプテン・リノ

『キャプテン・リノ』は、紙製の壁カードと屋根カードを使って高層マンションを積み上げていくバランス系ボードゲームです。プレイヤーは順番に壁を立て、その上に屋根カードを置いていきます。
屋根カードには特殊効果があり、順番を逆回りにしたり、次の人をスキップさせたりと、UNOのような駆け引きが展開されます。さらに「キャプテン・リノ」のコマを移動させる場面では、物理的なバランスが大きく変化し、タワーが崩れる緊張感が生まれます。手札をすべて使い切るか、タワーを崩さずに乗り切った人が勝利となります。
出典:Youtube ボードゲームルール超簡単説明より
| ジャンル | バランス・アクションゲーム |
| 効果 | 手先の器用さと集中力を養い、空間認識力と判断力が鍛えられる |
| 人数 | 2〜5人 |
| 時間 | 約10〜15分 |
| 特徴 | 屋根カードの特殊効果で戦略性が生まれ、コマがバランスを崩すスリル要素 |
犯人は踊る

『犯人は踊る』は、たった1枚の「犯人カード」をめぐってプレイヤー同士が駆け引きを繰り広げる心理戦型カードゲームです。プレイヤーは手札からカードを1枚ずつ出しながら、犯人カードの所在を推理し、探偵カードやいぬカードで犯人を当てることを目指します。
一方、犯人カードを持っているプレイヤーは、アリバイカードで身を守ったり、カード交換で所在をぼかしたりしながら、最後の1枚として犯人カードを出せれば勝利。「犯人は誰だ?」という緊張感と、カードが移動することで生まれるドラマが魅力の、短時間で盛り上がるパーティーゲームです。
出典:Youtube TRAMPLE GAMESより
| ジャンル | 推理ゲーム・心理戦・正体隠匿系カードゲーム |
| 効果 | 推理力・観察力・駆け引き・ブラフ・演技力の向上 |
| 人数 | 3〜8人(5人以上が特に盛り上がる) |
| 時間 | 約10〜20分 |
| 特徴 | カード交換や効果によって、犯人役が次々と変わるスリリングな展開 |
ルールの理解が育つ知育ゲームの工夫

知育ゲームは「楽しいだけでなく学びにもなる」ことが魅力ですが、その根本にはルール理解の力があります。9歳という年齢は、抽象的なルールや条件を少しずつ理解できるようになる時期であり、ゲームを通じてそれを実感することができます。
例えば「ナンジャモンジャ」や「ブロックス」は、それぞれ独特なルールを持ちながらも、繰り返し遊ぶことで自然とパターンを覚えていく設計になっています。こうしたゲームでは、最初にルールを理解し、それを守りながらプレイする力が養われます。また、「こうしたら負ける」「ああすれば勝てる」といった体験を通じて、ルールの意味や重要性も身につけていきます。
ここで注意したいのは、最初から複雑なルールのゲームを選ぶと、子どもが理解しきれずに嫌になってしまう可能性があるという点です。最初は簡単なルールのものを選び、「できた!」という体験を積ませることが、ルール理解への自信にもつながります。
知育ゲームは単に知識を増やすものではなく、「ルールを守る力」や「勝ち負けのバランス感覚」を育てるうえでとても有効です。日常生活や学習習慣にもつながる力が、遊びの中で自然と育っていくのです。
ナンジャモンジャ
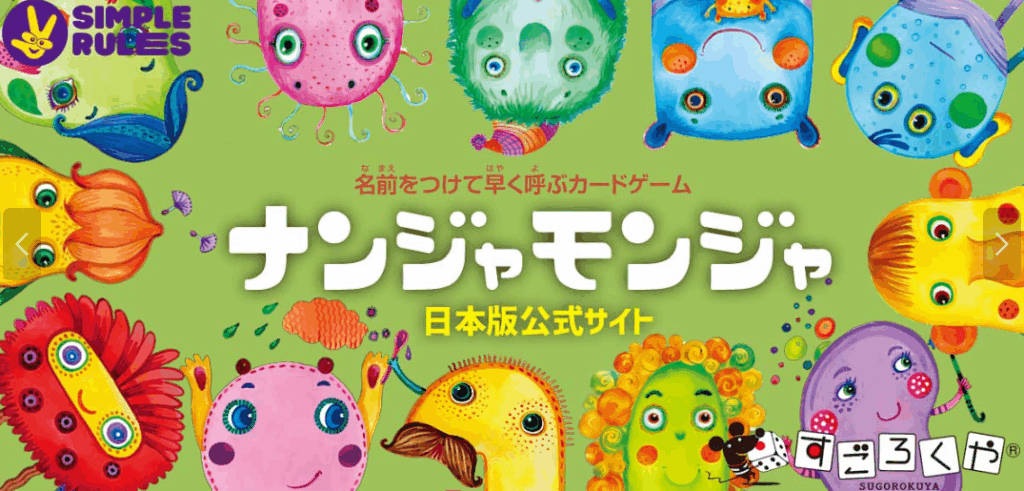
『ナンジャモンジャ』は、謎の生物が描かれたカードにプレイヤーが自由に名前をつけ、その名前を記憶していく記憶系パーティーゲームです。初めて見るキャラクターには命名を、すでに名前がついているキャラクターが出たら、誰よりも早くその名前を叫びます。正しく最速で名前を言えた人がカードを獲得し、山札がなくなった時点で最も多くのカードを持っている人が勝者となります。シンプルなルールながら、笑いと混乱が絶えない盛り上がり必至のゲームです。
出典:Youtube QuizKnockより
| ジャンル | 「記憶×瞬発力×ネーミングセンス」の融合型 |
| 効果 | 記憶力と注意力の強化と思考速度の向上 |
| 人数 | 2〜6人 「シロ」と「ミドリ」両方を混ぜれば最大 12人 まで対応可能 |
| 時間 | 約15 |
| 特徴 | 名前をつける自由度が高くセンスが試され、笑いが絶えない盛り上がり系ゲーム |
ブロックス(Blokus)

『ブロックス』は、色と形の異なるピースをボード上に配置し、できるだけ多くのピースを置いた人が勝ちとなる陣取り型ボードゲーム。
ピースは角と角だけで接続可能という独特なルールがあり、空間認識・戦略思考・妨害と回避の駆け引きが楽しめます。
| ジャンル | 陣取り・アブストラクト・戦略系 |
| 効果 | 空間認識力・計画力・柔軟思考・集中力・前頭葉活性化 |
| 人数 | 2〜4人(2人プレイ時は1人2色) |
| 時間 | 約20〜30分 |
| 特徴 | 角と角だけで接続する独自ルール・年齢問わず遊べる・妨害と回避の駆け引きが熱い |
社会性と反論受容を学ぶプレイ設計

ボードゲームにおいて「社会性」や「反論の受け入れ方」を育むためには、ただ遊ぶだけでなく、プレイの設計に工夫を加えることが重要です。9歳ごろの子どもは、自己主張が強くなる一方で、他者との関わり方を学ぶ時期でもあります。このタイミングで他人の意見に耳を傾ける練習をすることは、今後の人間関係に大きく影響します。
例えば「犯人は踊る」や「ナンジャモンジャ」などのゲームでは、プレイヤー同士で意見を交わしたり、戦略について話し合う場面が自然と生まれます。特に推理系のゲームでは、他者の見解を受け入れることで勝敗に影響する場面も多く、相手の考えを聞く姿勢や、自分とは異なる視点を尊重する気持ちが育ちやすいのです。
ただし、全員が納得できるようにプレイを進めるためには、大人がルールの整備や発言の順番管理を担うなど、環境づくりも欠かせません。子どもが意見を言いやすい空気や、反論されても否定されたと感じないような雰囲気を整えることが、学びを深める鍵になります。
ボードゲームは単なる遊びではなく、意見のやりとりや反論への対応を通じて、社会性を育てる訓練の場にもなります。プレイ設計の工夫によって、その効果をさらに引き出すことが可能です。
プレイヤーの工夫で広がる学びの効果

ボードゲームの魅力のひとつに、プレイヤー自身がルールや進め方をアレンジすることで、学びの幅が広がる点が挙げられます。特に9歳の子どもは、創造的な発想や問題解決能力が伸びる時期であり、自由な工夫がそのまま学習体験につながる可能性があります。
例えば「どうやったらもっと面白くなるか?」「ルールを少し変えたらどうなるか?」といった視点でゲームに取り組むと、自主性や柔軟な思考が自然と育まれます。ある家族では、勝者が次のゲームのルールを一部決める方式を取り入れることで、子どもたちの発想力や責任感が向上したというケースもあります。
また、同じゲームでもプレイヤーによって進行の仕方や戦略が変わるため、他人のプレイを見ることも大きな学びになります。「自分にはなかった発想だ」「この進め方もアリなんだ」と気づくことで、多様性を受け入れる土壌が養われていきます。
もちろん、自由な工夫にはトラブルもつきものです。ルール変更が原因で不公平感が生まれたり、勝ち負けへのこだわりが強すぎて衝突してしまうこともあります。そのため、事前に「みんなが楽しめるための工夫であること」を共通認識として伝えておくことが大切です。
こプレイヤー自身の工夫が加わることで、ゲームは単なる娯楽を超えた学習ツールへと進化します。子どもたちの主体性と創造性を引き出すためにも、あえてルールに余白を残してあげるのも一つの方法です。
日常生活に活かせる発達支援の視点
ボードゲームで得られる学びは、ゲーム中だけにとどまらず、日常生活にも自然と活かされていきます。子どもが家庭や学校などの実生活で求められる力――たとえば、空気を読む、順番を待つ、人と協力する、意見を聞くなど――を、ボードゲームの中で疑似体験できるからです。
例えば「自分の番が来るまで静かに待つ」といったシンプルな行動も、ゲームの流れの中では自然に身につきやすいものです。また、ルールを理解して守る経験は、公共の場でのマナーや、学校の決まりごとへの適応にもつながっていきます。
前述の通り、発言するタイミングや他人の意見を受け入れる姿勢を養うことは、日常の人間関係にも良い影響を与えます。兄弟やクラスメートとのトラブルが減ったり、自分の感情を言葉で伝えられるようになるといった変化が、保護者から報告されることも少なくありません。
一方で、ゲームだけに頼ってしまうと、場面に応じた対応が難しくなる場合もあるため、「日常にどう応用するか」を大人が丁寧にフォローしてあげることが必要です。「この前ゲームでも〇〇してたよね」といった具体的な言葉がけがあると、子どもは自分の行動を振り返りやすくなります。
発達支援としてのボードゲームは、遊びを通じて子どもの社会的スキルや日常の振る舞いを整える手助けになります。ゲームの外側にある生活場面にどう橋渡しするかを意識することが、支援の質を高めるポイントです。
ボードゲーム 発達支援 9歳に効果的な育成ポイントまとめ
- 協力型ゲームは他者との連携意識を高める
- 知育ゲームは自由な発想力を刺激する
- 推理系ゲームは状況を俯瞰する力を養う
- 感情理解ゲームは思いやりや共感力を育む
- 論理思考ゲームは筋道立てて考える習慣を促す
- 集中力ゲームは持続的な注意力を養成する
- コミュニケーションゲームは対話の姿勢を強化する
- 多人数ゲームは場の空気を読む力を高める
- 知育ゲームのルール設計は理解力を鍛える要素になる
- 反論や違う意見を受け入れる練習ができる
- プレイヤー同士の工夫が学びを深める鍵になる
- 日常生活でも活用できる発達支援の視点が身につく
- 勝敗以外の価値を学ぶ機会を作れる
- 年齢に合ったゲーム選びが成長を後押しする
- 楽しさの中に多角的な学びが自然と含まれる








